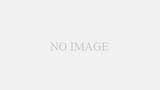出典
大橋昭一(2013),「観光学のあり方を求めて― 現状と展望」『観光学評論』,1(1),p5-17
メモ(引用を含む、下線は筆者)
そもそも観光とは何か、人間にとってどのような意味を持つものであるかを考えるところにある。本稿では、日本語でいう観光と、英語でいうツーリズムとは特に区別しないで、適宜用いている
要するに、人間が自宅など定住的場所を離れて、どこか観光地に行って、帰ってくることである。その意味では、観光のエッセンスは、「人が動く」ことであり、観光業の真義は「人を動かす」ところにある。
ちなみに、観光地の事を本で読んだり、テレビで見たりするのは、読書であり、テレビ視聴であって、観光ではない。
#この時の大橋先生はバーチャルツーリズム、オンラインツアーなどは想定していないようだ。
なぜ観光に行きたいと思うのか=プッシュ要因
「何か新しいことを知りたい、観たい、経験・体験したいという欲求」と、「日常的生活から脱却あるいは逃避したいという欲求」
レジャー目的、ビジネス目的およびその他の目的で、1年を超えない期間において、自己の定住的圏以外の地域を訪れ、滞在する訪問客で、訪問国で報酬を受ける仕事に就く者を除く
UNWTO
観光とは、余暇、ビジネス、その他の目的のため、日常生活圏を離れ、継続して1年を超えない期間の旅行をし、また滞在する人々の諸活動
国土交通省観光庁,2009「観光入込客統計に関する共通基準」
観光入込客とは、訪問地での滞在が報酬を得ることを目的としない者
国土交通省観光庁,2009「観光入込客統計に関する共通基準」
上記は統計目的の定義である。報酬を得ているかを調査するのは容易であるが、報酬がなければレジャーなのか、ビジネス目的なの帰省目的なのか区別は困難
交通業者や宿泊業者はこの定義で問題ない、供給者側の定義
観光研究は下記の3つがある
- 供給者サイドからの研究
交通機関や宿泊施設等の運営や、観光地の形成問題などが主たる研究課題
顧客がどのようなものであるかは、観光マーケティングの問題 - 需要サイドからの研究
観光客はどのような動機で観光に行くか、観光客満足はどのような時に起きるかなどが研究課題 - 需要サイドと供給サイドを統合したもの
観光に関与する産業・企業は、企業形態上は別々の産業・企業であっても、一つの観光業企業であるかのごとく考えてもいい、観光システム論
社会体制のとらえ方
- 現在の社会を資本主義社会ととらえ、そのなかで観光の問題を論究するもの
- モダン社会、あるいはポスト・モダン社会としてとらえるもの、現代ツーリズム論の主流的見解
オルタナティブツーリズムとは下記の通りだ
異なったコミュニティの人たちの間で行われる旅行の正当な形(just form of travel)を推進するプロセスをいうものであり、旅行関与者の間において相互理解、連帯性および平等を志向するものである
MacLeod, 1998, p.190
オルタナティブ・ツーリズムとは、要するに、地元民がツーリズムに関与できる範囲を拡大
Pearce, 1992
することによって、ツーリストにとっても、地元民にとっても、ツーリズムが真に有意義なものとなるようにするところに真義があるが、それを実際に容易に実現できる場は、さしあたり、宿泊施設であり、その運営、管理そして労働も地元民が行うようにすることが現実的であり、キーポイントとなる事柄である
オルタナティブ・ツーリズムという名のもとに、一種の選別主義的・排外主義的行為が行われてい
ること、少なくともそうした傾向のあることが痛切に指摘されている。
ツーリズムは、商品売買ではなくて、文化交流の場となるようなものにすべきであるというのである
が、その場合、ツーリストも地元民もそれぞれの文化を固定的なもの、静的なものと考えるのではなく、動的なものと考え、そのハイブリッドな統合を図るという見地にたつことが肝要
コメント、感想
オルタナティブツーリズムと言う言葉自体は知っていたが、どのような流れで出てきて、どのようなことなのか少しわかったと思う。いまいちピントきていないので、もう少しいろんな論文を読みこんで評論できるようになりたい。
以下、将来の自分のコメント