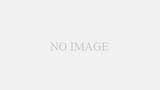出典
瀧端 真理子(2016),「日本の博物館はなぜ無料でないのか?―博物館法制定時までの議論を中心に―」,『追手門学院大学心理学部紀要』(10),p13-31
メモ(引用含む)
(入館料等)
博物館法第26条(令和4年施行令)マーカーはブログ執筆者によるもの
第二十六条 公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。
本論文は、日本の博物館法に「原則無料」規定がある理由を明らかにすることを目的とする。
日本の博物館入館料の実態
博物館入館料問題に関する先行研究
イギリスの場合
労働党政権が 2001 年に国立館を全面無料化した理由
「国内のあらゆる階層の人々が博物館・美術館に無料でアクセスできることが、国民の福利
厚生の向上につながる」ことが挙げられている。
一方で、無料政策に対する批判としては、
①訪問人数が増えてもリピーターが大幅に増えただけで訪問者の階級構成にあまり変化はないという
調査結果が存在するため、「国民全体の福利の向上」は無料化の正当化事由にならない、
②入場料に収入を依存する独立系館へ不利に働いているため、官による民業圧迫である、の 2 点が指摘
されている。
ニュージーランドの場合
結論としてすでに国民は税金によって博物館への支払いを済ませているのだから原則無料にすべき、と論じている。
増田辰良「博物館への入館料金をめぐる論争」北星学園大学『北星学園大学経済学部
北星論集』48-2、2009 年、p61-96
アメリカ
の博物館の 2/3 以上が無料日を設けていることを示し、入場無料の期間・時間帯を明示すること
が初来館・低所得の来館者を招く一般的な方法であり、その明示により正規の入館料を正当化出
来ることを論じている。
AAMの2013年報告書では、
入館無料または推奨入館料を示すのみの館は 36.8%、一般入館料(General admission fee)が存在する館は 63.3% あり、大人の一般入館料の中央値は$7.00 で、2009-2011 年の値と変化がない。また、92% の館が、何らかの機会に「誰でも無料」の機会を設けていることが示されている。
博物館法成立以前の『博物館研究』に掲載された入館料に対する考え方
(2)棚橋源太郎「博物館施設近時の傾向」(1929 年)
維持に差支ない限りは無料で入れると云ふことを原則としなければならぬ。
併しながら無料入場と云ふことは必ずしも無制限に人を入れると云ふことではないので
す。観覧の曜日と時間を制限し観覧の区域を限定する必要がある。美術館には特に其の必要
がある。公衆の運んで来る塵埃や日光、湿気、熱、振動等で陳列品に非常な損害を被むるか
らである。(中略)博物館を余り開放すると種々な弊害が起る、悪用される傾がある。
(6)関東庁博物館の入場料改定問題(1931 年)
関東庁当局の意向としては、この種社会事業は元来その性質上無料を理想と
し、殊に春秋を除いては寧ろ閑散を遺憾とする現状であるから、多分右料金の改正は実現せ
ぬであらう。
「博物館法」制定過程における議論
1950年「博物館動植物園法」の草案を出し、その中で入館料については「第十二条 国立及び都道府県立の博物館動植物園は、入場料を徴収しないことを原則とする。但し、土地の情況その他の理由により、場内整理のため必要あるときは、小額の入場料及び付帯設備の使用料を徴収することができる」と記述しており、自身の戦前の考え方を踏襲していることが分かる。
1954年度の調査(鶴田総一郎)
現在の日本にとっては有料入場はいろいろな意味での災害を防ぐためのよい意味の一種の入場制限になっている。また日本の大衆の心理として、無料ということは商業広告でなければやすっぽい見せ物というように感じてしまう妙な傾向があり、現在の有料制度は結構利点もあるのである。
「博物館法制定 10 周年記念座談会」
・古賀忠道(上野動物園長)「先の話の動物園協会の反対の一つは、“入場無料”という項をそ
のままとり、無料では絶対にやっていけない、つぶれてしまう。即ち“原則として”という
のをそのまま受けてしまった。」
・近藤春文「金をとれば博物館法が示す広く一般に提供することに反し、また研究調査を考え
る場合、図書館法のように無料でやることはあり得ない。」
博物館を無料とすべき根拠はどこにあるか
- ユネスコ勧告(博物館をあらゆる人に解放する最も有効な方法に関する勧告、1960 年)
「国民のあらゆる階層、特に勤労階級(原語では working classes)に博物館を利用せしめるよう奨励するため、あらゆる努力が払われるべき」と述べている。 - 図書館関係者の主張から得られるヒント
川崎良孝は、「アメリカの民主政体を支えるのは、開明化され、自力で的確な判断ができる住民である」「住民の能力を開発する教育、自力で的確な判断をする前提としての知識や情報の普及は公の責任に帰する。前者が公教育で、後者が公立図書館である。そして、それらはいずれも無償、無料でなければならないのである」と説明している。 - 「公教育無償の原則」からの類推は可能か
義務教育を国民に受け入れさせるための「無償制」であったという観点もある。高橋はその背景として、「産業革命がすすむにつれて、労働者に酒場と売春宿以外の健全なレジャー施設を与える方が結局は得であることが理解されるようになった。
終わりに
博物館法・図書館法ともに制定時に日本人の側から「無料制によってすべての人に教育の機会が与えられる」という考え方が育つには至らなかった。
しかし現在、各地の自治体は財政難に陥る一方で、少子高齢化の進行や貧困世帯の増加に直面しており、公立博物館は福祉などの他の施策と、減少する税金というパイを取り合わなければならない状況に置かれている。
博物館の理念として、また、寄附や納税者からの支持を得る意味でも、博物館関係者は格差是正のための努力(=不利益を被っている人々への積極的優遇措置)を、その有効性の検討も含めて視野に入れるべき時期を迎えているのではないだろうか。
博物館の入館無料を社会統制の側面から考察する必要があることを指摘しておきたい。
イギリスの博物館の無料政策は、佐藤が指摘するように、世界各地から文化財を収奪してきた過去を無視して考えることはできない。
入館料問題について考えることは、博物館を巡る様々な問題領域を照らし出す可能性を内包しているのである。
感想、コメント
非常に興味深い論文!!
博物館おける入場料について、海外の事例、過去の議論等がまとめられており、非常に貴重な論文である。参考文献を含めもっと理解しないときちんとコメントできないが、今の理解で下記書き殴ってみた。
改正博物館法においては、「原則無料」の条文に変化はなく、各館に任せると言う判断をしている。
これは各館により事情、状況が異なるので、仕方ない部分もあるが、課題の先送りのようにも感じた。
おそらく博物館関係者の本音は「全員無料にしたいが、それぞれの事情(前例、モラルハザード対策、一定の歳入の確保など)で難しい」だろう。
一方で、本当に「無料」が良いことなのか。「無料」にすれば、教育の平等な提供になるのだろうか。
これだけ、文化、娯楽が増えた現代においては、入場料の議論だけでなく、提供方法についても議論すべきだろう。