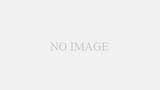出典
大友翔一(2021)「日本における夜間光と各種統計指標との相関関係」,『GIS-理論と応用』29(1),p23-28
メモ(引用含む)
人工衛星データの特徴=>大規模かつ、高頻度にデータ取得が可能
Henderson et al .(2012)は、複数の国家間の比較を行う場合に、夜間光を利用する統計枠組みの方が、既存指標よりも経済水準、社会活動の代理変数として不確実性を取り除ける可能性に言及している
今回の論文では、日本政府データと夜間光を比較。DMSPデータの2010年の平均値をtiffでダウンロード。500mポイントグリッドにて、シェイプファイル化→各市町村ごとに空間結合し、市町村ごとの夜間光の平均を計算。
小売店、飲食店、商業事務所、百貨店については上記データで相関があり、非常によく説明できた。
一方、医師数、歯科医師数、薬剤師数、医療機関数、水洗化人口に相関はなかった。
平均収入と夜間光については極めて弱い相関があった。
小売店舗や商業店舗のデータと関連性が強いことが確認された。一方、基礎的な社会インフラである、医療や下水道は一定程度は格差がなくなるように整備されているような関連性が確認された。
感想、コメント
日本の統計と夜間光について関連性が確認できたのはとても良いことだと思う。関連性はあるだろうと思われていたが、ちゃんと検証してくださったのは非常にありがたい。これにより夜間光データの価値が向上しただろう。
一方、DMSPだけでなく、VIIRSでも相関関係が見られるか確認するべきだろう。DMSP時系列データが2013年に終了し、VIIRS が現在まで利用可能であるし、VIIRSの方がダイナミックレンジも大きい。
今後の研究が期待される。