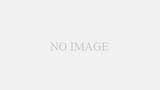出典
平成24年(ワ)第9969号 著作権侵害差止等請求事件(PDF)
メモ(出典より引用)
裁判所の判断
- 正距方位図法への変換について
そこで,星座板を作成するに当たっては,その使用目的に適うように,星及び星座の天球における極座標上の位置を,そのまま円形平面の極座標に転記するのではなく,実際に天空を観測した場合の星座の形状等を反映するように修正することが行われている。そのような修正をするに当たっては,実際の観測における星の位置関係を反映させる必要があることに加え,星座板自体の大きさの制約から,その修正をした後における星の位置関係等を含む表現の幅は限られたものとならざるを得ず,表現自体として差異化する(個性を表現する)ことのできる部分は少ない。 - 星座の選択について
教育目的から観測に適する主要な星座を選択し,観測に適さない星座を除くのが当然である。そうすると,学習用教材としての星座板に載せることのできる星座の数及びその種類の選択の幅は,自ずと限定されたものとならざるを得ない。 - 星座の特定方法及び星座線の結び方について
星座は,恒星の配置を便宜的な形象,すなわち神話・伝説上の存在に見立てて,天球を区分したものであるところ(甲25),星座に属する星の中から特定の星を選択して星座線で結び,当該形象を表すことは一般に行われている。また,星の明るさは,肉眼で観測することのできる最も暗い星が6等星であるから(甲7の1),星座線で結ぶ星を選択するに当たっては,それ以上の明るさを有する恒星の中から選択する必要があるし,星座名で表される神話・伝説上の存在を表すのに,ふさわしい恒星を選択して星座線で結ぶ必要もある。
これらのことからすると,星座の特定方法及び星座線の結び方に係る表現の選択の幅は相当に狭いといわなければならない。原告星座板についても,原告の主張及び証拠(甲4の2~4)によれば,各星座に属する1等星から4等星までの恒星の中から,各星座の名称が表象する形象を表現するのにふさわしい星を選択して星座線で結んだというにすぎないのであって,平凡かつありふれた表現であるというべきである。 - 星座名の記載
星座名自体はあらかじめ決まっているものであるし,前記アの学習用指導教材であるという販売・使用の目的や星座板自体の大きさ等も考慮すれば,文字のフォント,大きさ,位置等の選択の幅は狭いことが明らかである。 - 星の位置
現代の星の位置を前提とせざるを得ないのであって,選択の幅は著しく狭いというほかなく,この点に創作性を認めることはできない。 - 星座板上における星の位置の修正
一定の目的がある以上,選択の幅は,むしろ収束する方向へ働くのであり,現に,上記のとおり,その結果には大差がないことからすれば,平凡かつありふれたものと評価するほかない。したがって,これらの点についても,創作性のある表現ということはできない。 - 星の形
等級に応じて大きさを変えたり,色分けをしたりしている点も平凡かつありふれたものというほかない(なお,1等星から3等星までの色分けは,相違している。)。 - 天の川
天空で観測できる天の川に近いイメージを星座板上に再現しようとすると,その色彩や輪郭などを含む表現が,結果として,一定の範囲に収束しているものというべきである。
これらのことからすると,原告星座板に描かれた天の川の表現についても,平凡かつありふれたものというべきである。
感想
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
著作権法第2条2項
本件は星座早見盤の著作権侵害があったかが争われた事件である。著作権については「創作的に表現」したのかどうかが問われた。星座早見に使用されている星座線等については「創作的に表現」されたものではない(=一般的)と認められたことは興味深い。
各星座の名称と領域はIAUにより決められているが、星座線は国や文化によって異なる。日本においては藤井旭さんが考えた?広めた?結び方が創作性が認められないほど、一般的であることが明らかになったとも言えるだろう。